「治験(ちけん)」という言葉を耳にしたことはありますか?
普段の生活ではあまり馴染みのない言葉かもしれません。実際、「つぐみさんはどんな仕事をしているの?」と友人に聞かれ、「治験に関わっているよ」と話すと、「ちけん??」と聞き返されることが多いです。
医療の現場で働くスタッフですら、治験についてはよくわからない、聞いたことがないということもあります。
けれど、私たちが病気になったときに使うお薬は、必ず治験を経て世の中に出ています。
今回は、初めて治験という言葉を知った方でも分かるように、治験の基礎知識を少し詳しくご紹介します。
治験とは?
治験とは、新しい薬や治療法が「本当に安全で効果があるのか」を調べる臨床試験のことです。
製薬会社が開発した薬は、動物実験などの「非臨床試験」である程度の効果や安全性が確認されます。その後、人に使っても大丈夫かどうかを確かめるために行うのが「治験」です。
つまり、治験は 新しい薬が実際に医療現場で使えるかどうかを確かめる大事なステップ なんです。
また、治験と聞くと、なんとなく「怖い」や「怪しい」などのイメージを持たれる方もいるかもしれません。実際に、患者さんに治験の説明をしていく中で、「つまり実験ってことでしょ?こわいな」と話されていた患者さんもいました。
でも、実際には、GCPという厚生労働省が定めた厳しい基準と手順に従って実施されており、患者さんの人権が最優先となるように実施されています。
また、薬なので、副作用が出る可能性はあります。そのため、治験に参加していただいている間、患者さんは普段の通院よりも慎重に健康状態を確認されます。その中で、もし副作用など安全性に問題が見られたら、そのときには、医師の診察・治療がすぐに適切に行われるようになっています。
このように治験は、厳しく管理され、安全に配慮された環境で行われています。
【治験を実施するためのルール】
治験を行う製薬会社、病院、医師は「薬事法」というくすり全般に関する法律と、これに基づいて国が定めた「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(=GCP[Good Clinical Practiceの略])という規則を守らなければなりません。この規則は欧米諸国をはじめ国際的に認められています。【 法律・GCPで定められているルール 】
治験の内容を国に届け出ること
治験審査委員会で治験の内容をあらかじめ審査すること
同意が得られた患者さんのみを治験に参加させること重大な副作用は国に報告すること
製薬会社は、治験が適正に行われていることを確認すること
参考:厚生労働省 2.治験のルールhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/fukyu2.html
治験の流れ
治験は大きく分けて「第Ⅰ相」「第Ⅱ相」「第Ⅲ相」という3つのステップを踏んで行われます。
- 第Ⅰ相試験
少人数の健康な人や患者さんに協力してもらい、安全性や体内での動きを調べます。
→「どのくらいの量なら安全か?」を確認する段階です。 - 第Ⅱ相試験
実際に患者さんに使ってもらい、効果と安全性をさらに詳しく確認します。
→「効き目がありそうか?」を確かめる段階です。 - 第Ⅲ相試験
もっと多くの患者さんに参加してもらい、現在使われている薬と比べてどうかを調べます。
→「本当に実用できる薬か?」を最終確認する段階です。
このステップをクリアしてはじめて、国(厚生労働省など)の承認を受け、市販薬として使えるようになります。
治験に参加する人たち
治験にはさまざまな立場の人が関わっています。
- 患者さんや健康なボランティア(実際に治験に参加してくれる人)
- 医師・看護師(治験を行う病院やクリニックのスタッフ)
- 治験コーディネーター(CRC)(患者さんと医師の間に入り、サポートする役割)
- 治験依頼者(薬を開発している製薬会社など)
特に治験コーディネーターは、患者さんが安心して参加できるように説明をしたり、日程を調整したり、サポートする大切な役割を担っています。

治験は患者さん一人ひとりのご協力があってこそ、成り立っています。
治験はなぜ大事なの?
「新しい薬を待っている人」が世界中にはたくさんいます。
治験を通して安全性と効果が確認されなければ、その薬は使えません。つまり治験は 未来の医療を作るために欠かせないプロセス なのです。そして、この治験を円滑に進めるためにサポートするのが、私の仕事=CRCなんです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
「治験って意外と身近かも?」と思っていただけたら嬉しいです。
次回はもう少し踏み込んで、治験コーディネーターがどんなふうに治験に関わっているのかを紹介してみようと思います。


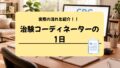
コメント